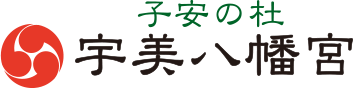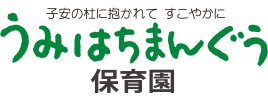福岡県糟屋郡宇美町平野部のほぼ中央に鎮座する、第十五代應神(おうじん)天皇御降誕の聖地について、「日本書紀」には、「『皇后新羅』より還り給う十二月十四日誉田天皇(應神天皇)を筑紫の蚊田に生み給う時今其の産所を號(なず)けて宇瀰という。」又、「古事記」には、「其の御子あれます其の御子の生地を號けて宇彌という。」とあり、江戸時代の儒学者 貝原益軒翁は、「この里は山中にあれど、四方平原にして広く、都邑ここにたつともゆたかなる所なりと、洵に山紫水明の佳境にて、神功(じんぐう)皇后皇子発祥地にふさわしい地なりと実にすばらしい里であると。」と称えられています。
主祭神である神功皇后・應神天皇の母子神、玉依姫命、住吉大神、伊弉諾尊の五柱がお祀りされており、八幡様は殖産文化の祖神として遍く崇敬されておりますが、八幡神御降誕の聖地と伝えられる当宮は、「安産・育児」の信仰が特に篤く、多くの方が安産祈願や御礼参り(初宮詣)に参拝されます。

應神天皇(おうじんてんのう) 神功皇后(じんぐうこうごう)
玉依姫命(たまよりひめのみこと) 住吉大神(すみよしおおかみ) 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

当宮は、神功皇后が三韓征伐より御帰還され、産所を蚊田の邑(蚊田は宇美の古名)に定め、側に生出づる槐(えんじゅ)の木の枝に取りすがって、應神天皇を安産にてお産みになられたこの地を宇瀰(うみ)その後、宇美(うみ)と称されました。御産舎の四辺に八つの幡を立て、兵士に守らせた故事が、「後世八幡大神と称するは此故なり」とも伝えられています。八幡大神御降誕の聖地として、敏達天皇の御宇(西暦570年頃)に創建され、先ず神功皇后と應神天皇の母子神をお祀り致し、後世に至りて上記の五座としてお祀りされました。境内には、樹齢二千年以上と推定される、国指定天然記念物「湯蓋の森」「衣掛の森」という二本の老大樟(くす)を始め、数多くの大樟が生い茂り、若葉の季節となれば、萌えるような御神威の「生命の息吹」を今日に伝えており、安産・育児の守護神、「子安大神(こやすのおおかみ)」と称され、今も多くの人々にお参り頂いております。

大正11年(1922)3月、国指定天然記念物として「衣掛(きぬかけ)の森」「湯蓋(ゆふた)の森」、昭和15年(1940)10月に、筑前四王寺跡経塚群出土品が国指定重要文化財、そして安産信仰に関する伝説地として、昭和30年(1955)9月に「子安(こやす)の木[槐]」「子安の石」「産湯(うぶゆ)の水」「胞衣(えな)が浦」等にまつわる、神功皇后と應神天皇の母子神に因む安産信仰の対象が、福岡県指定文化財(民俗資料)として一括指定されています。
また、古くから当宮に伝わる「宇美神楽」が、昭和48年(1973)11月に福岡県無形民俗文化財に指定されています。

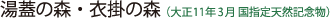
共に素晴らしい老大樟で、当宮のシンボルであります。「湯蓋の森」は、社殿に向かって右側、「衣掛の森」は社殿の左側にある老樹で、様々な人生儀礼を今日まで見守ってきた巨樹は、樹齢二千年以上とも推定されていいます。元禄2年(西暦1689)貝原好古「八幡本紀」第三巻には、「神功皇后新羅より帰らせ給い、香椎より巽の方蚊田の邑に御産屋を営まれこもらせ給う、御側に生い茂れる楠あり、其の下にて産湯をめさせ給う、その大木繁茂し枝葉ことにうるわし、後人これを名付けて湯蓋の森という。また産衣を掛けたるを衣掛の森という。」


神功皇后、産所を蚊田の邑(蚊田は宇美の古名)に定め、側に生出づる槐(えんじゅ)の木の枝に取りすがり、應神天皇を安産にてお産みになられました。その木は今もその種を絶やさず、「宇美宮の槐」として、皇后皇女を始め、産平安の衣木(みそぎ)には、必ずこの槐を用いたとされています。「平産の幸ある木」という意味で、「子安の木」と称されています。槐は中国の本草学によれば、解毒、補精に効果があり、その枝にすがれば安産するという信仰があります。


境内末社「湯方社」を囲むように、玉垣を築きこぶし位の石が山ほど積まれています。安産祈願を終えた妊婦が“お産の鎮め”として此処の石を預かって持ち帰り、目出度くご出産の暁には、別の新しい石にお子様の名前等を記して健やかなる成長を願い、安産御礼(初宮詣)の御祈願にてお祓いの後に、預かった石と一緒お納めするのが慣しとなっています。この「子安の石」の信仰はいつ頃始まったかは定かではありませんが、「筑前國続風土記」には記されております。


境内北隅にあり、「應神天皇御降誕の時、此の水を産湯に用い給いしより今に至るまで妊婦拝受して安産を祈る。」と伝えられています。表示石の揮毫者は、県内初の内閣総理大臣、廣田弘毅翁の年令十三歳のときの揮毫によるものが刻まれています。

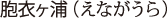
胞衣(えな)は、産舎の後なる川(宇美川)にてすすぎ、筥に入れて山(胞衣ヶ浦)に奉安したとされ、その地を「胞衣ヶ浦」と称し、祠を建てお祀りしています。
[境内北神苑内]


明治34年(1901)に再興された神楽で、糟屋郡内に広まっていた流れをくみ、舞風はまことに清楚で神への敬謙さを良く表しています。神楽座員の奉仕により、御誕生大祭(正月初舞)、春季大祭(子安大祭)、秋季大祭(宇美放生会大祭)に奉納されております。
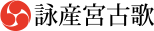
| 萬代集 | 諸人をはくくむ答ありてこそ うみの宮にはあとをたれけめ | 藤原家隆 |
| 拾玉集 | かけまくも長けれども産の宮 我が皇神にしろしあらませ | 慈鎮 |
| 夫木集 | 朝日さす香椎の杉にゆうかけて くもろずてらせ世をうみの宮 | 西行 |
宇美八幡宮の境内は、「子安の杜 (こやすのもり)」と称され、 二千年以上 の生命をつなぎ、今なお亭亭として聳える三十余の大樟 (くす) は、 長い風雪 に耐えながら、世の移り変わり、人々の営みを見守ってまいりました。
神職、巫女は毎朝毎夕、 大樟の下でその氣に包まれ、 悠久の時の流れと、 生命の尊さを教えられながらご奉仕させて頂いております。
新しい生命の授かりへの願い、 安産、 そして健やかなる成長など、 お参り される皆様、お一人お一人の思いとお姿を拝しながら、心よりその成就を 日々お祈り申し上げております。
折々に、心の拠りどころとして 「子安の杜」 の氣に触れ、 お参り頂けることを お待ち申し上げております。 お子様そしてそのお子様と幾世代にも亘って、 宇美八幡宮の子安大神様は見守り続けてくれるものと存じます。